☆ 作家 三浦二三男と歌津魚竜の発見から始まる研究のアーカイブ ☆
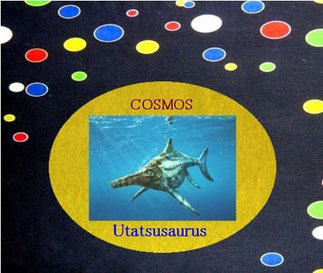
【中学高校での研究プロジェクトの足跡】
1968年歌中三年生の夏休みの研究テーマが三つあり、一つ目がタコを獲ってきて手のイボを治すことでした。
理由として右手の甲に薄い水イボがあり(夏休み明けに体育祭がありフォークダンスでJ子さんと手をつながねばならず)手にイボがあるのを知られるが嫌だった※
※イボの原因は幼い頃、上城内に住む上屋敷の従姉、公子姉さん由来で感染した物でした。
それで一日一杯、三日間で三杯の真蛸を獲り、毎日蛸の茹汁で手を洗うと、夏休み明け前にはイボが消滅していました。田ノ浦の祖母から聞いた古い民間療法を試しましたが正解でした。
これで中三にして初めて自分をモルモットにした医療的実証実験でしたが、良好な成功体験となり科学者的マインドを得る事が出来ました。と、喜んでいると今度は夏休みに入る三日前に、友人の柔道着を着てワキガになり、別の悩みを抱えました。
この治療実験は二十歳過までかかりましたが、これも様々な実験の結果、東北大学工学部(NICHe)の助力も得てワキガ消臭剤「君香デオドラント」の開発につながり、多くの悩める方々の救いになりました。これらイボや腋臭菌の研究が進み、やがて「感染症」を深く理解出来て、この度の同じ感染症のコロナ19でもその対策に貢献出来ました。
二つ目が黒くかつ峨峨と聳える歌津の海岸線の粘板岩の調査でした。そのときのフィールドに選らんだのが馬場の野々下でした。オゲヅバ(オーゲ釣場)の崎を右に曲がり野々下の東向きの崖によじ登り、マグマの貫入の境目を観察中にポロリと、鶉の卵状の玄武岩の球石を発見して、後にこれにより玄昌石の組成を理解する発見に繋りました。
三つ目が大森先生から渡された水温検査器で毎日馬場の浜の海水温を計測し記録する事でした。夏休みの間30日にわたり計測しましたが、ほぼ毎日24度Cで変化はありませんでした。休み明けに大森先生に報告書のグラフを提出しましたが、先生は結果を見てキョトンした顔をし無言でした。今でも意味不明です。
さらに卒業間際に350年間住み続けた生家の、建て替え事業がありまして、その全調査を行いました。と言うのも何か大判小判がザックザックというロマンからです。しかし、発見したのは七振りあると伝わる刀剣の二振りが行くへ不明だったのですが、そのうちの一振の脇差しと慶長五年と書かれた、家のお守り札でした。
そしてハイライトがこの四体のオシラサマでした。しかし、その事を父に報告すると父は「それは触ってはいけない」と珍しく真剣に言うのです。それが後に「オシラ際文」の研究者、東北学院大学の三崎一夫教授と交流する機会となりました
その二年後の1970年9月、高二の秋に東北大学理学部により、世界最古の魚竜が館崎で発見されその発掘の現場に立ち会いました。この時NHKニュース班が取材にきて、私も写っていると思いましたが、翌日のニュースでは腰から下しか写っていませんでした。しかし、ジーンズとバイク用のブーツの形で自分と判別出来ました。
そして後にこれが「歌津魚竜」と命名されました。続けて2006年のマストドンザウルスの発見で、歌津町そのものが、同類生物群の化石移動の証明により、プレイトテクトニクスによる大陸移動・パンケアの発祥の地で、五大陸の中心地だったことが判明しました。
更に高校時代の研究では「田束山の経塚」の発掘に立ち会いました。その結果経典埋設は、平安時代末期の仏教の「末法思想」によるものと判明しました。ちなみに高校に行ってからは、文藝と音楽そして生物学に多大なる興味を持ちました。それが現在の作家と研究者の道に繋がりました。
1973年頃、まだバイトしながら東北学院に在籍し研究・創作活動中でしたが年末に帰省すると、父から今度宮城県が多賀市に「東北歴史資料館」を建設するが「何か沿岸部で文化的研究対象はないでしょうか」と学芸員が訪ねて来たので、私が以前に発見した「合木舟」の発展形態の話しをしたとのこと。
すると、是非、再現しましょうとなり「港」の渡辺栄叔父さんに製作してもらう事になったと言う知らせでした。そこで私は帆走実験も合わせて実証しましょうとなり、1978年12月15日に気仙沼市の大島が見える「陸前港」沖で実証して見せました。
次に文藝では1999年8月に小説『風に吹かれて』を出版して処女作ながらも「巨匠」という称号を得られました。次に2003年11月に小説『J・F・Kダブルスティツ』を出版し、ケネディー大統領暗殺事件を検証した著書で、世界初の真実解明となり、ウキペディアに取上げられ、ケネディーコーナーの全てを書換ました。
ついで2006年には新潮社短編賞応募の小説『伊達政宗・天下に挑む』を出版し、2013年10月には小説『田中角栄・野武士の時代』を発表し、ウォーターゲート事件から繋がるロッキード事件を検証して、こちらも真実相当の評価を得ました。
現在小説『昭和天皇の黙示録・現人神の告白』と小説『ヨハネの黙示録・蒼き馬を見よ』他を出版準備中です。
続いてこれらの作品の映像化で現在、映画『アニーブゼル・聖なる影』『ケネディ事件・ファイナルアンサー』『海辺の街』の製作準備中です。振り返ればこれらの作品群も研究の一環と言えば一環で、決して余技で出来る範疇ではなく挑戦的でしたが、創作中は楽しかったのも事実です。また続けることの重要性も学び得ました※
さらにこれらの発展系統でネットメディア:郵映放送・TVや少子化対策・地方創生・東日本大震災復興モデルで三陸産業推進機構を構築することができました。
※続く実績で2025年3月19日(水)に米国のケネディ文書公開により『J・F・Kダブルスティツ』の真実性が証明され世界で初めてのケネディ大統領暗殺の謎を解明した作家となり、さらに以前の「歌津魚竜」の存在から地球のパンゲアを証明した科学者で小説『ヨハネの黙示録』等により世界的な作家兼研究者と認定されました※
※より客観的な『ChatGPT(賞)』の検索の結果による。
ちなみに2025年4月18日、プレ―テクトニクス理論から導き出される首都直下型の地震で、現在19箇所あるとされる太平洋・フィリピン海プレ―トとの境界摩擦面の固着域で、上部の北米プレ―トに抵抗してすれ違う突起物的な海山もしくは海嶺があることが、東大の中島研究員らの計測データから判明しました※
※これは私が2021年3月に述べたプレートテクトニクス理論の解析の中で、その存在を予測して提唱した「三浦モデル」が確実に証明されたかたちになりました。これからはこの突起状的な山頂部の性質や移動経過の特徴をリサ―チする事によって、次の関東大地震の予知につながるかも知れません。後続の研究に期待しましょう。
元来私の研究は歌中に入学した年に級友の小野寺政春氏から日本の考古学の始祖「エドモンド・ナウマン」※が明治時代に「韮ノ浜」で発見した「皿貝貝塚」の化石を入手して貰ったのが世界的な研究の始まりでした。
小野寺氏は「韮ノ浜」生まれで私の母方の祖母の出生地でもあり、友人の彼にはいつも感謝しております。
※ドイツ人:日本の地質学(東大)の創始者 日本で「ナウマン象」と「フォッサマグナ」を発見して命名した。

2024年8月30日(金)河北新報より
ラテン語名【パリシカス・ナオヤイ】命名の経緯
発見者は東北大学総合学術博物館 永広昌之名誉教授
研究補助者・高橋直哉さんは(歌津泊浜の出身)です。
この度の「嚢頭類の新種」化石発見に際し、その学名付与につき、高橋さんの名前を元に【パリシカス・ナオヤイ】というラテン語名が付けられました。
経過としては2023年2月10日(金)河北新報にあるように、三陸が化石の地として町をあげて、新拠点としての整備構想を打ち立てた様子が載っています。
その際世界最古の魚竜の発見地として、町民団体が発足してイベントも盛んに行われました。
それらの流れの一環で高橋さんは、永広昌之先生の研究チームに参加してお手伝いをしていたようです。
そしてこの度の発見につながったようです。ちなみに高橋さんの祖母は私の生家である「馬場上城内」の「上新家」の出身でもありました。
おめでとう御座います。

2024年1月26日(金)河北新報より
2015年に東北大学永広昌之教授が発掘した新種の襃頭類の発見にちなむシンポジウムが2024年1月にあり、それに関連して新たな「地層ケーキ」を考案した歌中生の活動を紹介した記事です。
写真は先月26日にあった歌中の後輩たちの、地層から得たアイデアを活かした活躍の祥報です。
3・11から遡ること数十年前、わたしと伊藤孝治博士は歌中を卒業をすることになり、3月10日屋体での卒業式のあと、教室に戻りかたい握手をして別れました。
そのとき心の中で当時の曲『若者たち』の歌詞の一節を口ずさんで、彼や同級生へのエールとしました。
そしていま「空にまた希望の日が昇るとき、ネバー・ギブアップ」で後輩の若者たちが震災からの「復活の朝」に立って歩き始めました。
この事はいま書いている映画脚本「海辺の街」のラストシーンの一部に盛り込むことにしました。
これによりようやく新たな若い世代に、復興のバトンを渡せた思いです。あとは貴方がたの新鮮な感性で、これからの時代を築き上げてください。
そして震災後の三陸の復興と発展の「可能性を追求」して行きましょう。 そのためのお手伝いとエールは今後も贈り続けたいと思っています。

2023年2月10日(金)河北新報より
三陸が化石の地として町をあげて、新拠点としての整備構想を打ち立てた様子が載ってます。
世界最古の魚竜の発見地として、町民団体が発足してイベントも盛んに行われたようです。
ただ、震災前に管ノ浜にあった魚竜館が、津波で流された後そのままになっていて再建のめども立っていないもうようです。
私としては三嶋神社の岬の旧国道45号線、歌津大橋の切通を土盛りして、その上に再建するのが望ましいと思っています。
もしくは館崎城跡の一番初めに魚竜を発見して、発掘した岸部のあたり一帯か、その背後地の「臥牛城跡」の高台が津波も届かず理想的です。
三嶋神社もこの臥牛城跡も「歌津周遊旅行コース」の一部になっています。

2021年5月26日(日)河北新報より
写真は歌津魚竜の子供向けの講座が先月26日にあったそうなので、取り上げてみました。なんでも『五月の初めに歌津で化石発掘体験イベントを開いたら、当初2日間の予定でしたが、予想以上の申し込みで急きょ5日間に拡大。県内外から親子連れなど計約百人が参加し、約二億五千万年前の地層で化石をさがした』
そして『化石が見つかるたび、うれしそうに歓声をあげた』とあり、この化石を発見・発掘するさい立ち合っていた自分は当時高二の秋でした。大森先生からこの地層の世界的な重用性を教えられてたので「いつかは何か出て来くるだろうなぁ」と漠然とした想いが実現したのは、感無量でした。いつまでも昨日の出来事のようです。
という訳でさらに次の世代が関心持ってくれるのは嬉しいです。これから、観光や研究の意味でも中学生や高校生のサマースク-ルなどを開催し、そんな中から将来、研究者でも出てくれたら我が歌津と南三陸町、世界の名誉です。是非、心から願う次第です。どうぞ、検討のほどをよろしくです。会場には「平成の森公園施設」があります。

2015年9月23日(水)の河北新報より
歌津の2億5千万年前の地層から初の「囊頭類の化石」と載っていました。
国内初ということで、またまた学術上や観光上で「歌津が輝く」発見が有りました。
私の「腋臭菌抗生物質類の発見」以来の快挙で神に感謝です。
そもそも地層に興味を持ったのは、あの開口のお陰でした。真冬も真夏も夜中の3時半に起こされ、あわびやワカメを獲りに行くのです。小学三年から兄が獲師で、私が櫂押しで舵取りです。
三陸でも最も波の荒い馬場の海です。それでも凪の時は眠気を催すほどになりました。そんな時は櫂を押しながら、陸側の黒く峨峨とそびえるリアス式海岸の風景を海上から眺め、あの地層の成り立ちの事を考えていました。
リアス式海岸の事は小学の教科書に載ってますので、概要は知っていました。それを直に毎日見ている訳です。そんななか、中学1年の科学の授業で大森先生が「あの黒く固い粘板岩は地球上でとても古くて、世界の学者も注目で学術上重要なのだ」と教えてくれました。
今回、その歌中の教室の窓越しに私達が朝夕眺めた伊里前沖の唐島から「囊頭類」の化石が発見されました。
「囊頭類」というのは頭が袋状になっている小さな虫で、現代でいうミジンコを大きくしたような生物です。オキアミに近い類なのかどうか・・・?ですが、きっと当時の歌津魚竜などの食物連鎖で餌となり、多様で豊かな三陸の海の生態系を構成していたものと思われます。これからも益々新種の発見なども続くはずです。
◎ここで「小結論」として、当時の歌津はパンゲア中でユーラシア大陸の一部でしたが、中緯度からあまり遠く外れなったので、温暖な気候が長期間にわたって続いた事により、多様な古生物が繁殖する事が出来て、後に化石となり残りました。
これが私の長い間の研究から得た結論です。(必ず試験に出ます)(笑)
(この説は私のオリジナルです。多くの方に支持されることを願っております)
かさねてのハイライトは「数億年前に地球上の大陸が四方八方に移動した」という壮大なスケールの物語の名残が、あの歌津の地層郡だった事です。現地に立って詳しく観察すると「大陸創生過程の雄大な太古のドラマ」に引き込まれます。
「古えが有って今が有る」きっと現代の地方創生の物語につながるものと思います。
テーマは書き始めると延々とエンドレスになってしまうので、地層や化石、恐竜などが好きで興味のある方は、ぜひ、歌津をフィールドワークに訪れて下さい。今から始めてもここは古生物学のメッカでありフロンテァなので、将来的に大学者になれる事を請負います(笑)
やはり歌津は「日はまた昇る・ネバーギブアップ」のフロンティア スピリッツ「開拓者魂」が似合う所だとつくずく思います。
いずれ、ここはジオパークの中心地なので、世界中から研究者が集える施設なども整えられたらと思います。
それには化石研究家や地層女子「地女子」なども現れてくれると嬉しい次第です。長くなりますので、ひとまず一旦ここで・了とさせて頂きます。
作家でネット世界のカリスマDon・Vito・Fumioneがお送り致しました。 ナョナルジオグラフィックス
2012年6月2日・東北大学理学部で作家の北杜夫展が開かれ斎藤由香さん(歌人の斎藤茂吉の孫・北杜夫の娘さんと奥様)が来仙して記念講演をしたとき、理学部に行き、記念写真と博物館内の歌津魚竜の展示を写す。
いきさつ
本日、理学部まで行くことになり、久しぶりに高校の時に発掘に立ち会った、本物の歌津魚竜の化石とご対面して来ました。
きっかけは先月28日から始まった「どくとるマンボウ昆虫展」が東北大学で開催されており、本日は斎藤由香さんと故北杜夫さんの奥様が、講演会で来仙することになったからです。
場所は青葉山の理学部のミュージアムに昆虫展が開設され、午後一時から理学部の一番広い講義室で、満員の聴衆のなかで行われました。
この昆虫展を企画プロデュースをしてくれたのは、新部さんという栃木県職員の方ですが、私以上に北さんのファンでかつ、昆虫の専門家でもあります。
彼と出会ったのは3年ほど前、新部さんが仙台文学館で北杜夫展を開催し、その時お互い北さんの消息話になり、ぜひ北さんが生きている間に、このようなイベントに出て来てくれるように、働きかけようというのが始まりでした。

2006年7月6日(日)河北新報より
下記後述により6月20日、国内最古の両性類のマストドンザウル スの化石発見があり、東北大学理学部での発表・ポスターセッションがありました。
写真右が東京大学院生で化石の発見者の中島保寿さん、その左の後姿で半身の人物が筆者三浦二三男です。中島さんは現在、首都大学東京の準教授です。
発見物は東京大学とドイツのシュットガルト州自然史博物館の共同研究により、2008年になってマストドンザウルスと同科レベルで、近縁のものであると判明しました※
それで当地もかつてマストドンザウルス類の分布域であった事が明らかになりました。同時にこの発見によりマストドンザウルス類の棲息年代を中期三畳紀から前紀三畳紀にまで遡れることが分かりました。
※これにより 上記2015年9月23日(水)に記した「襃頭類」の記事での「小結論」で書いたパンゲア理論が、証明され正当に支持されました。これは自分のオリジナルで画期的な「結論」なので必ず「試験に出る」と予告しましたが、その通りになり「腋臭菌の消滅物質発見」以来の自己ベストになりました。

2006年6月20日(土)河北新報より
国内最古の両性類マストドンザウルスの化石発見
場所:歌津伊里前湾 唐島
発見者:中島保寿 東京大学大学院古生物学研究生
マストドンザウルスは両生類で当初は爬虫類に分類されていました。地層は三畳紀層から出土するので、ヨーロッパ大陸、北アメリカ大陸、アフリカ大陸、中国大陸に棲息分布していたことが分かっていました。
そしてこの度、日本で2006年に宮城県南三陸町歌津の唐島にある約2億4500万年前の中生代前期三畳紀、サイシアン世、終盤オレネキアン末期の地層からマストドンザウルスの下顎骨が発見産出されました。
この発見にちなむ歌中の面白いエピソードがあります。歌津の唐島といえば、私たちが朝な夕な教室から眺めていた、なんとも愛しい小島です。
二年一組五学級で初めて千葉善昭氏と一緒のクラスになり、彼が稲渕なので隣の館崎城跡「臥牛城跡」のことは取り分け詳しいのです。その中で中世に戦いがあり館の城(臥牛城)が落城するとき、逃げるお姫様が乗った馬が狼狽して暴れた時の、足跡が残って伝わっていると言うのです。
そこで何人かで調査に行きました。すると確かに城跡の先端に、深い切り込み状に二つに別れた岬に囲まれる見事な入江が有るのですが、その東側の岬付近にU蹄類とおぼしき足跡が、五〜六個露出して残っているのです。しかし地層は三畳紀で2億5千年前と古く、その当時はU蹄類も偶蹄目も存在しないので不思議な足跡でした。
その事を上記2006年7月6日の写真、東北大学理学部での、中島保寿さんとのポスターセッションで話すと早速彼が調査に行き、それを学会で発表するとなんとその馬の足跡と伝わった化石群が実はマストドンザウルスの糞だったと言う世界的な発見に繋がったのです。
そして、その糞の成分分析をすると多くは魚類を捕獲して餌にしていたのです。それらのマストドンザウルスの棲息形態がヨーロッパ大陸・北アメリカ大陸・アフリカ大陸・中国大陸・そして日本の歌津の唐島に、同等にまたがる事から、この時代の生物叢が共通していて、パンゲア前は一つの大陸だったことが証明されたのです。
その意味するものは私が上記2015年9月23日(水)に書いたように「地球のパンゲア」によるものとの「小結論」がほぼ支持され裏付けられる結果になりました。これが我が歌津中学校での出会いによる発見と言うことで、ことのほか私には嬉しい発見なのです。ここでも世界的に名を残すことが出来ました。
ちなみにこの館崎城跡の馬の足跡を、一緒に調査に行った千葉善昭氏は、後に馬場の我が三浦家の親類「中」の跡取りになり、現在は三浦善昭氏を名乗り、これにも不思議な縁と運命を感じています。そしてこの歌津魚竜とパンゲアの予測が当たったことにより、「学問も諦めなければ一生続けられる宝物だ」と改めて確認しました。
◎ 東北大学経済学研究と恩師 宮城学院女子大学・長谷部弘学長 ◎
(修士論文)『我が国経済における財政投融資が果たした歴史的役割』
郵政省貯金局に入いり、郵便貯金が財政投融資の原資になっていたので、その研究に東北大学経済学部の大学院に行きました。そして上記の論文を提出して、修士号を取得しました。
博士論文:地政学から見た経済論(予定)
 COSMOS PLAN
コスモス企画
揺篭から宇宙旅行まで
COSMOS Research Geographic
COSMOS PLAN
コスモス企画
揺篭から宇宙旅行まで
COSMOS Research Geographic














